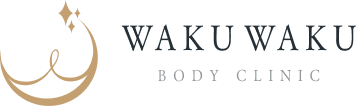産休の期間はいつからいつまで?知っておきたい基礎知識
「産休って、結局いつからいつまで取れるんだろう?」
出産を控えたプレママのあなたは、このような疑問を抱えていませんか?
産休は、ママと赤ちゃんにとって大切な休息期間です。
しかし、その期間や制度について「よくわからない」と感じている方も少なくないでしょう。
この記事では、産休の期間に関する基礎知識を分かりやすく解説します。
また、具体的な統計データも交えながら、あなたの疑問を解消し、安心して産休を迎えられるようサポートします。
1.産休とは?まずは基本を押さえよう

産休は「産前産後休業」の略で、労働基準法によって定められた女性労働者の権利です。
この制度は、妊娠中の女性が安心して出産に臨み、出産後に心身を回復させるための期間を保障することを目的としています。
1-1.産休の目的と重要性

産休の最も重要な目的は、母子の健康を守ることです。
妊娠・出産は女性の身体に大きな負担をかけます。
産休があることで、無理なく出産準備を進め、出産後は育児に専念し、心身ともに休養することができます。
また、産休は女性がキャリアを中断することなく、出産後も働き続けられるよう支援する役割も担っています。
安心して出産・育児ができる環境は、女性の社会進出を後押しする上で不可欠です。
1-2.産休と育休の違い
「産休と育休って何が違うの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
簡単に言うと、以下の通りです。
産休(産前産後休業): 出産を控えた女性と、出産後の女性のための休業。労働基準法で定められています。
育休(育児休業): 子どもを養育する男女が取得できる休業。育児介護休業法で定められており、原則として子どもが1歳になるまで(特別な事情がある場合は最長2歳まで)取得できます。
この記事では、主に産休の期間に焦点を当てて解説を進めます。
2.産休の期間はいつからいつまで?具体的な日数と計算方法

産休は「産前休業」と「産後休業」の2つに分けられます。
2-1.産前休業の期間

産前休業は、出産予定日を基準に取得できる休業です。
多胎妊娠(双子以上)の場合: 出産予定日の14週前(98日前)から取得できます。
単胎妊娠(一人の出産)の場合: 出産予定日の6週前(42日前)から取得できます。
いずれの場合も、出産予定日は期間に含まれます。
例えば、出産予定日が8月1日であれば、単胎妊娠の場合は6月20日から産前休業に入ることができます。
この期間は、請求があった場合に与えられるものです。
つまり、本人が希望すれば出産直前まで働くことも可能です。
ただし、母子の健康を第一に考え、無理のない範囲で休業を取得することをおすすめします。
2-2.産後休業の期間

産後休業は、出産日の翌日から取得できる休業です。
出産日の翌日から8週間(56日間)は、原則として就業させてはならないと労働基準法で定められています。
ただし、産後6週間を経過した後に、医師が「支障がない」と認めた業務に限り、本人が希望すれば就業することも可能です。
しかし、多くのママがこの期間は身体の回復と新生児との生活に専念するため、無理に働くことはほとんどありません。
2-3.出産が予定日より遅れた・早まった場合
出産は、予定通りに進まないことも多々あります。
もし出産予定日より遅れたり、早まったりした場合はどうなるのでしょうか?
出産が予定日より遅れた場合: 産前休業は、実際の出産日まで延長されます。この場合、産前休業の日数は予定より長くなります。
出産が予定日より早まった場合: 産前休業の日数は短くなりますが、産後休業の期間(8週間)は変わりません。
いずれの場合も、産前産後休業の期間は法律でしっかり保障されているので安心してください。
3.産休中の給料はどうなる?出産手当金と社会保険料

産休中は会社を休むため、給料が支払われないのが一般的です。
しかし、生活の心配をすることなく産休に専念できるよう、「出産手当金」という制度があります。
3-1.出産手当金とは

出産手当金は、健康保険から支給される手当です。
会社員や公務員など、健康保険に加入している方が対象となります。
支給条件:
1.健康保険の被保険者であること。
2.妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること(死産、流産、人工妊娠中絶も含む)。
3.産休中に賃金の支払いがない、または賃金が出産手当金より少ない場合。
支給期間: 産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までの範囲で、仕事を休んだ期間が対象です。
支給額: 「支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3」が1日あたりの支給額となります。
出産手当金は、産休中の生活を支える重要な収入源となるため、忘れずに申請しましょう。
申請は、産休が始まってから、もしくは産後休業が終わってから会社を通じて行います。
3-2.産休中の社会保険料免除
産休中は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が免除されます。
これは、被保険者と事業主の両方に適用されます。
免除期間: 産前産後休業開始月から終了予定月の前月まで。育児休業等期間と同様に、月単位で免除されます。
メリット: 社会保険料の負担がなくなることで、手取り額が増えるだけでなく、将来受け取れる年金額にも影響はありません。
社会保険料の免除を受けるためには、会社を通じて「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
4.産休取得に関する統計データで見る日本の現状

日本の女性がどれくらい産休を取得しているのか、具体的な統計データを見てみましょう。
これらのデータは、厚生労働省の「令和4年度雇用均等基本調査」に基づいています。
4-1. 産休の取得状況
日本の女性労働者の多くが、産休制度を活用しています。
産前休業取得率: 90.0%
産後休業取得率: 97.3%
特に産後休業は、労働基準法で就業が義務付けられていない期間であるため、ほとんどの女性が取得していることがわかります。
この高い取得率は、産休制度が女性にとって不可欠なものとして認識されている証拠と言えるでしょう。
4-2. 育児休業からの復職状況

産休後の育児休業を経て、職場に復帰する女性の割合も非常に高くなっています。
育児休業終了後に復職した女性の割合: 94.8%
このデータは、産休・育休制度が単に休業期間を保障するだけでなく、女性がキャリアを中断することなく、出産後も働き続けられるよう支援する役割をしっかりと果たしていることを示しています。
出産と仕事の両立を希望する女性にとって、復職支援は非常に重要な要素です。
4-3. 企業の育児休業制度導入状況
企業側も、女性が安心して出産・育児を行い、職場復帰できるような環境整備に努めています。
育児休業制度を導入している企業の割合は、2023年のデータ(厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」)で99.7%に上ります。
ほぼ全ての企業が育児休業制度を導入していることは、社会全体で女性の活躍を支援しようという意識が高まっていることを示唆しています。
これにより、女性は自身のキャリアとライフイベントをより柔軟に計画できるようになっています。
これらの統計データは、日本において産休・育休制度が広く浸透し、女性が安心して出産・育児と仕事の両立を図れるような社会環境が着実に整備されつつあることを物語っています。
5.産休期間を充実させるための準備と過ごし方

産休の期間を有効活用し、出産・育児に備えることは非常に大切です。
5-1.産休に入る前の準備
1.仕事の引き継ぎ:

産休に入る前に、担当業務の引き継ぎを丁寧に行いましょう。引継書を作成したり、後任者への説明時間を設けたりすることで、スムーズな移行が可能です。
2.会社の制度確認: 会社独自の産休・育休制度、福利厚生などを事前に確認しておきましょう。企業によっては、法定以上の手当や支援がある場合もあります。
3.出産・育児の情報収集:

産休中に役立つ出産準備品の情報や、新生児のお世話に関する知識を調べておきましょう。
4.休息の確保:

妊娠後期は身体が疲れやすくなります。無理なく、十分な休息を取ることを心がけましょう。
5-2.産休中の過ごし方
1.身体の回復を優先: 出産後は、まずは自身の身体を休ませることが最優先です。無理な家事や外出は控え、ゆっくり過ごしましょう。
2.赤ちゃんとの時間:

新生児との触れ合いは、かけがえのない時間です。授乳やおむつ替え、抱っこなどを通じて、赤ちゃんとの絆を深めましょう。
3.情報収集と交流: 育児に関する情報収集や、地域の育児サークル、SNSなどを通じて他のママとの交流を図るのも良いでしょう。孤立せずに、悩みを共有できる仲間を見つけることは大切です。
4.行政サービスや助成金の確認:

各自治体で提供されている子育て支援サービスや、助成金についても調べておきましょう。例えば、乳幼児医療費助成や、ベビーシッター利用補助など、活用できる制度はたくさんあります。
5.パートナーとの協力: 産後うつやワンオペ育児にならないためにも、パートナーと育児や家事の分担について話し合い、積極的に協力を仰ぎましょう。
5-3.産休明けの働き方計画

産休期間中に、産休明けの働き方についても考えておくと良いでしょう。
時短勤務の利用: 育児と仕事の両立のために、時短勤務制度の利用を検討してみましょう。
保育園探し:

職場復帰を考えている場合は、早めに保育園探しを始める必要があります。地域によっては待機児童問題があるため、情報収集は早めに行動しましょう。
キャリアプランの再考: 育児を機に、自身のキャリアプランを見直す人も少なくありません。改めて、今後の働き方や目標について考えてみる良い機会です。
6.まとめ:安心して産休期間を過ごすために

この記事では、産休の期間について、その基礎知識から具体的な日数、関連する手当や統計データまで幅広く解説しました。
重要なポイントは以下の通りです。
産休の期間は、出産予定日の6週前(単胎)または14週前(多胎)から産後8週間です。
産休中は「出産手当金」が支給され、社会保険料が免除されます。
日本の産休取得率は非常に高く、多くの女性が制度を利用しています。
産休期間は、身体の回復と赤ちゃんとの時間を大切にし、復職に向けた準備も進めましょう。
産休は、ママと赤ちゃんにとって非常に大切な期間です。
この期間を安心して過ごせるよう、制度を正しく理解し、必要な準備を進めてください。
もし疑問や不安な点があれば、会社の担当部署や社会保険労務士、自治体の窓口などに相談してみることをお勧めします。
この記事を書いた人
山下 こうすけ

わくわくボディクリニック代表 | 美容・健康業界の第一人者
2003年、セラピストとしてキャリアをスタートし、2010年に「わくわくボディクリニック」を創業。
独自に開発した20年以上の研究に基づく施術メソッドが高く評価され、現在では年間15,000人以上が来店する人気サロングループへと成長を遂げる。
また、その高い専門性と技術力が評価され、ミス・ジャパンの審査員も担当。
美容・健康に関するセミナー講師として、多くの女性の美と健康をサポートし続けている。
現在も施術の最前線に立ちつつ、最新の美容・健康トレンドを取り入れながら、多くの女性の「美」と「健康」をサポートし続けている。